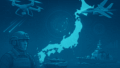2025年5月の勤労統計から見える構造問題と転換の必要性
はじめに:「生活の崖」に直面する現実
2025年5月に公表された毎月勤労統計(速報値)は、単なる経済指標ではない。
これは今、私たちの暮らしに何が起きているのかを克明に物語る「生活のレントゲン写真」である。
名目賃金は前年比+0.8%とわずかに上昇したものの、同時期の消費者物価指数(CPI)は+3.5%。
結果、実質賃金は-3.1%と5か月連続でマイナス成長となった。
「働いても生活が苦しくなる」──この“逆転現象”が常態化しつつある。
まさに、経済成長の果実が生活の現場に届かず、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条が、制度の現場で空洞化している。
本稿では、この統計を起点に、構造的な貧困の実相と背景を7つの視点から多角的に検証する。
そして、既存の制度がいかに貧困を生み出し、生存権を損なっているかを明らかにし、政策の転換点として必要な処方箋を提案する。
賃金と物価の乖離:生活を圧迫する“静かなスタグフレーション”
実質賃金のマイナス幅は深刻だが、その背後にはより切実な問題がある。
特に、食料・エネルギー・生活必需品の価格高騰が、可処分所得のごく大きな部分を奪っている。
家計調査によると、年収300万円以下の家庭では、これらへの支出が家計全体の50%を超えている。
大企業と中小企業の賃上げ格差(+2.5%対+1.2%)、全労働者の37.2%を占める非正規雇用の定着、そしてOECD平均を下回る労働生産性(74.5%)──これらすべてが“低賃金構造”を固定化させている。
加えて、円安と輸入依存(食料60%、エネルギー90%)が物価上昇を構造的に引き起こしており、生活の土台が静かに削り取られている。
可処分所得の罠:「年収の壁」と制度設計の逆機能
日本の制度設計は、善意の理念が「現場」で逆効果を生む典型例を見せている。
社会保険料と消費税の負担を加味すると、**実質的な可処分所得は2024年時点で-1.2%**と減少。
これは生活の選択肢そのものを狭める結果を生んでいる。
特に「106万円・130万円の壁」は女性やパート層の就労を抑制するトリガーとして作用し、慢性的な人手不足と労働供給制約の一因にもなっている。
また、消費税の逆進性は、低所得層に相対的に重くのしかかる。
年収200万円の層が負担する消費税率は12%、一方で年収2000万円の層では4%にとどまる。
このような制度的不公平が、社会の再生産を困難にしている。
雇用の格差:「働き方改革」と外国人労働政策の副作用
本来、労働環境の改善を目指した「働き方改革」も、現場では想定外の副作用を生んでいる。
とりわけ残業上限(月45時間)の設定は、低賃金層の収入減少に直結し、パート層では月2万円以上の手取り減少というケースも報告されている。
さらに、外国人労働者(2025年時点:約200万人)の受け入れが、賃金水準の抑制圧力として機能しており、特に低賃金・過酷業務の職場では、日本人労働者との摩擦が表面化しつつある。
貯蓄率の急低下:可視化される生活の脆弱化
2025年の家計貯蓄率は1%未満と、過去最低水準に近づいている。
特に単身世帯や高齢者世帯では、**生活費を貯蓄から取り崩している層が22.5%**に達する。
冷暖房の利用制限や食費の削減など、健康リスクと隣り合わせの生活防衛が広がっている。
年収300万円以下の層における「貯蓄ゼロ率」は31.8%。
災害・病気・失業といった予測不能の事象に対する“社会的耐性”が、制度的にも個人レベルでも急速に失われている。
セーフティネットの限界:制度の“使いにくさ”が排除を生む
生活保護の受給者数は約199万人。
前年比+5.2%と増加傾向だが、捕捉率はわずか20%にとどまる。
つまり、本来制度にアクセスすべき人の5人に4人は利用できていないという現実がある。
SNS(X)上では、「申請したら親族に連絡された」「窓口で門前払いされた」といった声が頻繁に見られる。
こうした制度設計そのものがスティグマを内包し、弱者を排除する構造を形成している。
地域に刻まれる「生存の格差」
都市と地方の平均賃金差は1.3倍。
東京の平均賃金が約45万円に対し、地方は27万円前後にとどまる。
東京の平均賃金は約45万円で、金融やITなど高賃金職種が集中。
厚労省の調査(2013年)では月収36.5万円だが、ボーナスや残業代で45万円に。
地方は農業や製造業が主で、平均27万円。
青森県は23.2万円と東京との差が大きい。
都市部は住宅費(手取りの35〜45%)が家計を圧迫し、地方は医療アクセスや教育機会が限定的。
つまり、どこに生まれ、どこで暮らすかが、その人の「生存条件」を決定してしまっている。
このような機会不平等の固定化は、地域間格差を広げ、地方の若者の流出と都市への富の集中という負のスパイラルを加速させている。
生存に不可欠な支出が「贅沢」になった社会
医療、住宅、教育という「生存の三本柱」に対する支出は年々厳しさを増している。
医療費は外来ベースで月平均5,750円、住宅費は東京1Kで9〜13万円、私立大学進学には総額1,200万円、塾代も含めれば年間80万円に達する。
もはやこれらの支出は中間層にとっても“贅沢”となりつつある。
教育格差は将来の所得格差に直結し、階層の固定化をもたらす。
結果として、国家全体の人的資本形成に重大な制約が生まれている。
憲法25条と経済政策の再定義:「誰を守るか」が問われる時代へ
これらの構造的な問題は、単なる経済の結果ではなく、**“政策が生み出した貧困”**に他ならない。
PB(プライマリーバランス)黒字化という財政目標に縛られた緊縮財政は、生存権を支える制度を制度疲労へと追い込んでいる。
求められるのは、「支出削減」ではなく「選択的再分配」である。
最低賃金の大幅引き上げ(1,600円目標)、累進課税の強化、生活保護制度の捕捉率向上、社会保険料の再設計、年収の壁の撤廃、そして地方への再投資──これらを通じて、憲法25条の実現に向けた**“財政の再定義”**が不可欠だ。
結論:「働いても報われない社会」からの脱却を
いま必要なのは、統計数字の読み解きにとどまらない、「人間の尊厳」に根ざした政策転換である。
働くことが苦しみを生む社会は、長期的に見て経済の活力も失う。
雇用、福祉、教育、地域──あらゆる分野で再分配と再投資が求められている。
経済政策とは、単に「何に使うか」ではなく、「誰を守るか」である。
いまこの瞬間、私たちは問い直さねばならない。政策とは誰のために存在するのか、と。